「糸井重里の萬流コピー塾」 1 [BOOK]
ネットで探し物をしていたところ、かつての愛読書がKindle版にて販売されているのを見かけたので、懐かしさのあまり押入れから引っ張り出してきた。
いつだったか絶版と聞いていただけに、いかなる形であれ、復刻は嬉しい知らせである。
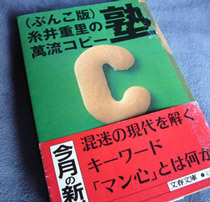
本書は、コピーライターの糸井重里氏が『週刊文春』に連載していた読者参加型の企画を、文庫版として編集したものである。
毎週、誌面で出されたテーマに対し読者がコピーを投稿、それを氏が批評するといった極めてシンプルな構成であった。
昔から言葉遊びの類いが好きだった私は、学生時代にその本と出会い、すぐさま夢中になった。
わずか数文字が軽やかに綴る人生模様は、川柳が十七文字で描くユーモアとウィットに溢れた世界とも相通ずるものがあり、その発想や工夫にニヤリとしたり唸ったり、飽きることなくページを捲ったものである。
内容的には大喜利に近いが、そこは「コピー」と謳うだけに、いくら面白くともネガティヴなだけの作品は評価されない。
マイナスの要素や下ネタをいかにポジティヴに表現し、商品(=テーマ)の価値を高めるかというところも見どころであった。
何はさておき、まずは実例をご覧いただこう。
テーマ 「コロッケ」

(世田谷区代沢「フランス屋」 手づくりコロッケ)
連載上は24回目ともなるお題だけに、糸井氏(以下、企画に合わせ「家元」という)の理念や評価のコツを心得た巧みな投稿が目立った。
“庶民派”をアピールしつつも、いかにただの“庶民派”で終わらせないか、というあたりがポイントではなかろうか。
なお、コメントは私の所感なので、ご了承のほど…
「おっ、トンカツの匂いがついてる」
オマケ戦略。
「新妻の、2ケ買う事のほこらしさ」
小さな幸福の正しい描き方。
「彼ったらね、いきなり熱いものをあたしの口の中に入れてくるの」
小さな幸福の曲がった描き方。
「肉屋から八百屋への挑戦状」
肉屋のショーケースにでも貼ってあれば面白いと思うが、家元も「これは大書きしたりするとカドがたつ」と評しているので、平和的なこちらも載せておこう。
「肉屋を父に、八百屋を母に」
「テーブルの冷めたコロッケをみて、つい何も盗らずに、出てきてしまった」
電子レンジが一般的でなかった時代ならではの哀愁。
が、忘れてはならない、コロッケが一家の危機を救ったことを!
「毎月二十四日はコロッケの日です」(※)
そう、コロッケは人にも財布にも優しいのである。
……等々。
そして、この回の最高評点の作品がこちら。
「落しても、食える」
なんという庶民感!なんという愛情!なんという付加価値?![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif) 「ねっ、手練れにない、強烈な素直さが、心に波紋をひろげるでしょう。」とは、家元の評である。
激しく同意、お見事としか言いようがない。
なにぶん初出が'83年からの連載物であり、また、とりわけ時代を敏く反映するというコピーの性格上、若干古めかしさを感じさせるお題や回答も目立つが、それはそれ、思い切って昭和レトロを楽しんでしまえばいい。
一方で、今なお色褪せない普遍的な説得力を持つコピーも見受けられるから面白いのだ。
「じゃがいも冥利につきます」とか「うー。ソースが身にしみる」なんてのは、今一つコピーとしてのインパクトには欠ける(したがって、家元の評価点は得ていない)が、じわじわと“心にしみる”良作ではないだろうか。
コロッケがスーパーやコンビニで買える時代に、やれ肉屋だ八百屋だなどとのたまっている本が、「Kindle版」での復刻ということにも感慨を覚える。
いずれにせよ、この回に止めてしまうのは惜しいので、また追い追いご紹介しようと思う。
「ねっ、手練れにない、強烈な素直さが、心に波紋をひろげるでしょう。」とは、家元の評である。
激しく同意、お見事としか言いようがない。
なにぶん初出が'83年からの連載物であり、また、とりわけ時代を敏く反映するというコピーの性格上、若干古めかしさを感じさせるお題や回答も目立つが、それはそれ、思い切って昭和レトロを楽しんでしまえばいい。
一方で、今なお色褪せない普遍的な説得力を持つコピーも見受けられるから面白いのだ。
「じゃがいも冥利につきます」とか「うー。ソースが身にしみる」なんてのは、今一つコピーとしてのインパクトには欠ける(したがって、家元の評価点は得ていない)が、じわじわと“心にしみる”良作ではないだろうか。
コロッケがスーパーやコンビニで買える時代に、やれ肉屋だ八百屋だなどとのたまっている本が、「Kindle版」での復刻ということにも感慨を覚える。
いずれにせよ、この回に止めてしまうのは惜しいので、また追い追いご紹介しようと思う。
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
いつだったか絶版と聞いていただけに、いかなる形であれ、復刻は嬉しい知らせである。
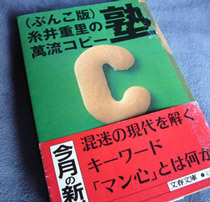
本書は、コピーライターの糸井重里氏が『週刊文春』に連載していた読者参加型の企画を、文庫版として編集したものである。
毎週、誌面で出されたテーマに対し読者がコピーを投稿、それを氏が批評するといった極めてシンプルな構成であった。
昔から言葉遊びの類いが好きだった私は、学生時代にその本と出会い、すぐさま夢中になった。
わずか数文字が軽やかに綴る人生模様は、川柳が十七文字で描くユーモアとウィットに溢れた世界とも相通ずるものがあり、その発想や工夫にニヤリとしたり唸ったり、飽きることなくページを捲ったものである。
内容的には大喜利に近いが、そこは「コピー」と謳うだけに、いくら面白くともネガティヴなだけの作品は評価されない。
マイナスの要素や下ネタをいかにポジティヴに表現し、商品(=テーマ)の価値を高めるかというところも見どころであった。
何はさておき、まずは実例をご覧いただこう。
テーマ 「コロッケ」

(世田谷区代沢「フランス屋」 手づくりコロッケ)
連載上は24回目ともなるお題だけに、糸井氏(以下、企画に合わせ「家元」という)の理念や評価のコツを心得た巧みな投稿が目立った。
“庶民派”をアピールしつつも、いかにただの“庶民派”で終わらせないか、というあたりがポイントではなかろうか。
なお、コメントは私の所感なので、ご了承のほど…
「おっ、トンカツの匂いがついてる」
オマケ戦略。
「新妻の、2ケ買う事のほこらしさ」
小さな幸福の正しい描き方。
「彼ったらね、いきなり熱いものをあたしの口の中に入れてくるの」
小さな幸福の曲がった描き方。
「肉屋から八百屋への挑戦状」
肉屋のショーケースにでも貼ってあれば面白いと思うが、家元も「これは大書きしたりするとカドがたつ」と評しているので、平和的なこちらも載せておこう。
「肉屋を父に、八百屋を母に」
「テーブルの冷めたコロッケをみて、つい何も盗らずに、出てきてしまった」
電子レンジが一般的でなかった時代ならではの哀愁。
が、忘れてはならない、コロッケが一家の危機を救ったことを!
「毎月二十四日はコロッケの日です」(※)
そう、コロッケは人にも財布にも優しいのである。
……等々。
そして、この回の最高評点の作品がこちら。
「落しても、食える」
なんという庶民感!なんという愛情!なんという付加価値?
寺山修司と澁澤龍彦 [BOOK]
寺山氏の代名詞とも言える「書を捨てよ、町へ出よう」とのフレーズが、実はアンドレ・ジッドの『地の糧』に由来していたことを、恥ずかしながら前稿の下調べの最中に初めて知った。
ジッドについては、澁澤龍彦も著書『快楽主義の哲学』の中で、こんな一文を紹介している。
「幸福になる必要なんかありはしないと、自分を説き伏せることに成功したあの日から、幸福がぼくのなかに棲みはじめた」 (『新しき糧』より)
甚だ無責任なことに、直にジッドの作品に当たってはいないので、「書を捨てよ…」にせよ「幸福になる必要なんか…」にせよ、いかなる文脈で書かれたものか定かではないのだが、印象として、両者の言わんとしていることに、それほどの懸隔があるようには思われない。
元より、『新しき糧』は『地の糧』の続編的性格の作品である。
澁澤は先の引用文についてひとしきり説いたのち、こう述べている。
「幸福のことなんか頭の中から追い出して、まず実際に行動すること。そうすれば、楽しさはあとからやってきます。」
「書を捨てよ、町へ出よう」の真髄も、案外こんなところにあるのではないだろうか。

('71年公開映画のポスター ※1)
ところで、ジッドを引いて「幸福」を説いた澁澤は、果たして“町へ出た”のであろうか?
澁澤は生涯四度に渡る欧州旅行に加え、中近東へも取材旅行に出かけており、また、国内各所の古刹を巡っていたなどと聞けば、大いに“町へ出た”ようにも思われるが、実のところ頻繁に旅するようになったのは'70年(澁澤42歳)の初渡欧以降であり、先のエッセイを上梓した5年も後の事である。
遠出に関しては腰が重く、相応の積極性をもって旅行を計画するようなタイプでなかったことは、例えば龍子夫人や巖谷國士氏の回想(※2)を俟つまでもなく、本人が「もともと自分は決して旅の好きな人間ではない(※3)」と白状している。
「書を捨てよ、町へ出よう」の寺山氏をジッドとするならば、当時の澁澤はジャン・コクトーに準えられよう。
コクトーについては、以前 拙稿で『大胯びらき』について触れたが、『ポトマック』にも次のような一節がある。
「旅行したまえ、とペルシケエルが僕に言うのだった。じっとしたまま汽車に乗っていさえすれば、君のまわりでいろんな物体や生物は移動するんだ。君は旅行をすると、君の見かたが新しくなるのか、それとも単に君の眼に映るものが新しいだけなのか、どっちだか分るかね? (中略)
ところで僕は、じっと動かないでいて、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。」
断じて“自分の行為を無益と感じ”てなどいなかったことを除けば、かつての澁澤が作中の「僕」タイプの人間であったのは間違いのないところであろう。

さて、澁澤について語られる際に少なからず象徴的に用いられる言葉に、「胡桃の中の世界」および「壺中天」というものがある。
「胡桃の中の世界」は、『ハムレット』劇中の「たとえ胡桃の殻のなかに閉じこめられていようとも、無限の天地を領する王者のつもりになれる(※4)」という台詞に由来する概念であり、「壺中天」は、仙人と一緒に小さな壺に入ると、そこには俗世間を離れた別世界が広がっていたという後漢の故事に由来する。
これらについて、澁澤は「小宇宙はすべて、大宇宙の忠実な似姿なのであり、私たちの相対論的な思考は、そこに必ずミニアチュールの戯れを発見するのである。(※4)」と、相変わらず軽妙洒脱に説いている。
私がここで「胡桃の中の世界」と「壺中天」を持ち出したのは、こういうことである。
すなわち、天井までの書架にぎっしりと詰まった書籍とそこから溢れ出たそれらの山が、まさしくミニアチュールの象徴たる地球儀の据わった重厚な洋机を取り囲み、ベルメールやシモンの球体関節人形が妖しげな興をさかす自宅の書斎こそが、実は澁澤にとっての“胡桃”であり、“壺”ではなかったかと。
むろん、この場合に“胡桃”や“壺”の中に広がる世界は、およそ我々が物語に没入する際に彷徨うような浅はかで情緒的な夢空間とは異なり、該博な知識とそれを統べる明敏な知性に豊かな想像力が作用して初めて構築される、現実の「忠実な似姿」としての仮想現実空間であり、澁澤はこの世界にあって、ある時はプリニウスと、ある時はブルトンと、またある時はパラケルススやニコラ・フラメルと壮大な旅を続けていたのではあるまいか。
しかるに、頻繁には遠出をしなかったという言わばフィジカルな一面のみをもって澁澤が“町へ出なかった”と断じることには、いささかの躊躇いを覚えるのである。

(澁澤邸書斎 / 撮影:細江英公 「鳩よ!」’92年4月号より)
実際、寺山氏も、澁澤については「万象の偶然性を、想像力によって組織できるドラマツルギーの持主」であり、「ただのユートピア庭園の祭司ではない」とその稀有な才能を高く評価し、並の夢想家、文筆家とは明確に区別している。
しかし同時に、澁澤の示したミニアチュールの“サイズ”について、「それは、ときとしては胡桃の中にとじこめられるほどのものだが、ときとしては地球全体を一個の胡桃としてとらえられるほどのものに変わってしまう。」と、澁澤の語る「相対論的な思考」を踏襲しながらも、「「途方もなく拡張した球体」状の幻想を前にして、澁澤自身の日常の現実とは何か? ということが、この場合の課題である。」と問題提起までしている。
あくまでも私見であるが、フィジカルにも行動的であった寺山氏にしてみると、澁澤の“胡桃”や“壺”の中での活躍を最大限に評価しつつも、「ミニアチュールの戯れ」に甘んじた内向の嫌い無きにしもあらず、といったところではなかっただろうか。

(寺山氏が書評の対象とした『洞窟の偶像』と『東西不思議物語』)
寺山氏の書評が読書専門誌に掲載された'77年といえば、澁澤三度目の欧州旅行の年に当たる。
それを知ってか知らずか、記事には作風の変化を歓迎するような、こんな一節もある。
「長いあいだ、書斎にとじこもり、知識の地下納骨堂で、少年奴隷たちと「遊びにふけっていた」澁澤は、ここへ来て現実への関心をしめしはじめている。」
同じ時代を生きていたにも拘らず、残念ながらお二方が親しく交流していたことを示す資料はない。
“両雄相まみえず”といったところかも知れぬが、私などは不謹慎にも、真っ黒に日焼けしたランニング姿のわんぱく坊主が、家に閉じこもって本ばかり読んでいる近所の上級生を、「いいから遊びに行こうぜ!」と誘っている光景などを思い描いてはニヤついたりしている。
捕虫網の奇妙な虫を興奮しながら翳す下級生に、後からしぶしぶ付いて行った青っちろい少年は、涼しい顔でそのラテン語の“学名”を諳んじてみせるのである。
私もまた、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。
※ 寺山氏の書評に関する引用は、すべて「『洞窟の偶像』『東西不思議物語』」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)による。
〔参考〕
※1 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より
榎本了壱デザイン。
※2 「『滞欧日記』の真相」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)、『澁澤龍彦の古寺巡礼』ほか
※3 『旅のモザイク』あとがきより
ただし「いったん旅の軌道に乗ってしまうと、だんだん上機嫌になって興趣のつきるところを知らない」とも書いている。
※4 『胡桃の中の世界』より
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
[更新履歴]
'13.12 表現の一部修正
ジッドについては、澁澤龍彦も著書『快楽主義の哲学』の中で、こんな一文を紹介している。
「幸福になる必要なんかありはしないと、自分を説き伏せることに成功したあの日から、幸福がぼくのなかに棲みはじめた」 (『新しき糧』より)
甚だ無責任なことに、直にジッドの作品に当たってはいないので、「書を捨てよ…」にせよ「幸福になる必要なんか…」にせよ、いかなる文脈で書かれたものか定かではないのだが、印象として、両者の言わんとしていることに、それほどの懸隔があるようには思われない。
元より、『新しき糧』は『地の糧』の続編的性格の作品である。
澁澤は先の引用文についてひとしきり説いたのち、こう述べている。
「幸福のことなんか頭の中から追い出して、まず実際に行動すること。そうすれば、楽しさはあとからやってきます。」
「書を捨てよ、町へ出よう」の真髄も、案外こんなところにあるのではないだろうか。

('71年公開映画のポスター ※1)
ところで、ジッドを引いて「幸福」を説いた澁澤は、果たして“町へ出た”のであろうか?
澁澤は生涯四度に渡る欧州旅行に加え、中近東へも取材旅行に出かけており、また、国内各所の古刹を巡っていたなどと聞けば、大いに“町へ出た”ようにも思われるが、実のところ頻繁に旅するようになったのは'70年(澁澤42歳)の初渡欧以降であり、先のエッセイを上梓した5年も後の事である。
遠出に関しては腰が重く、相応の積極性をもって旅行を計画するようなタイプでなかったことは、例えば龍子夫人や巖谷國士氏の回想(※2)を俟つまでもなく、本人が「もともと自分は決して旅の好きな人間ではない(※3)」と白状している。
「書を捨てよ、町へ出よう」の寺山氏をジッドとするならば、当時の澁澤はジャン・コクトーに準えられよう。
コクトーについては、以前 拙稿で『大胯びらき』について触れたが、『ポトマック』にも次のような一節がある。
「旅行したまえ、とペルシケエルが僕に言うのだった。じっとしたまま汽車に乗っていさえすれば、君のまわりでいろんな物体や生物は移動するんだ。君は旅行をすると、君の見かたが新しくなるのか、それとも単に君の眼に映るものが新しいだけなのか、どっちだか分るかね? (中略)
ところで僕は、じっと動かないでいて、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。」
断じて“自分の行為を無益と感じ”てなどいなかったことを除けば、かつての澁澤が作中の「僕」タイプの人間であったのは間違いのないところであろう。

さて、澁澤について語られる際に少なからず象徴的に用いられる言葉に、「胡桃の中の世界」および「壺中天」というものがある。
「胡桃の中の世界」は、『ハムレット』劇中の「たとえ胡桃の殻のなかに閉じこめられていようとも、無限の天地を領する王者のつもりになれる(※4)」という台詞に由来する概念であり、「壺中天」は、仙人と一緒に小さな壺に入ると、そこには俗世間を離れた別世界が広がっていたという後漢の故事に由来する。
これらについて、澁澤は「小宇宙はすべて、大宇宙の忠実な似姿なのであり、私たちの相対論的な思考は、そこに必ずミニアチュールの戯れを発見するのである。(※4)」と、相変わらず軽妙洒脱に説いている。
私がここで「胡桃の中の世界」と「壺中天」を持ち出したのは、こういうことである。
すなわち、天井までの書架にぎっしりと詰まった書籍とそこから溢れ出たそれらの山が、まさしくミニアチュールの象徴たる地球儀の据わった重厚な洋机を取り囲み、ベルメールやシモンの球体関節人形が妖しげな興をさかす自宅の書斎こそが、実は澁澤にとっての“胡桃”であり、“壺”ではなかったかと。
むろん、この場合に“胡桃”や“壺”の中に広がる世界は、およそ我々が物語に没入する際に彷徨うような浅はかで情緒的な夢空間とは異なり、該博な知識とそれを統べる明敏な知性に豊かな想像力が作用して初めて構築される、現実の「忠実な似姿」としての仮想現実空間であり、澁澤はこの世界にあって、ある時はプリニウスと、ある時はブルトンと、またある時はパラケルススやニコラ・フラメルと壮大な旅を続けていたのではあるまいか。
しかるに、頻繁には遠出をしなかったという言わばフィジカルな一面のみをもって澁澤が“町へ出なかった”と断じることには、いささかの躊躇いを覚えるのである。

(澁澤邸書斎 / 撮影:細江英公 「鳩よ!」’92年4月号より)
実際、寺山氏も、澁澤については「万象の偶然性を、想像力によって組織できるドラマツルギーの持主」であり、「ただのユートピア庭園の祭司ではない」とその稀有な才能を高く評価し、並の夢想家、文筆家とは明確に区別している。
しかし同時に、澁澤の示したミニアチュールの“サイズ”について、「それは、ときとしては胡桃の中にとじこめられるほどのものだが、ときとしては地球全体を一個の胡桃としてとらえられるほどのものに変わってしまう。」と、澁澤の語る「相対論的な思考」を踏襲しながらも、「「途方もなく拡張した球体」状の幻想を前にして、澁澤自身の日常の現実とは何か? ということが、この場合の課題である。」と問題提起までしている。
あくまでも私見であるが、フィジカルにも行動的であった寺山氏にしてみると、澁澤の“胡桃”や“壺”の中での活躍を最大限に評価しつつも、「ミニアチュールの戯れ」に甘んじた内向の嫌い無きにしもあらず、といったところではなかっただろうか。

(寺山氏が書評の対象とした『洞窟の偶像』と『東西不思議物語』)
寺山氏の書評が読書専門誌に掲載された'77年といえば、澁澤三度目の欧州旅行の年に当たる。
それを知ってか知らずか、記事には作風の変化を歓迎するような、こんな一節もある。
「長いあいだ、書斎にとじこもり、知識の地下納骨堂で、少年奴隷たちと「遊びにふけっていた」澁澤は、ここへ来て現実への関心をしめしはじめている。」
同じ時代を生きていたにも拘らず、残念ながらお二方が親しく交流していたことを示す資料はない。
“両雄相まみえず”といったところかも知れぬが、私などは不謹慎にも、真っ黒に日焼けしたランニング姿のわんぱく坊主が、家に閉じこもって本ばかり読んでいる近所の上級生を、「いいから遊びに行こうぜ!」と誘っている光景などを思い描いてはニヤついたりしている。
捕虫網の奇妙な虫を興奮しながら翳す下級生に、後からしぶしぶ付いて行った青っちろい少年は、涼しい顔でそのラテン語の“学名”を諳んじてみせるのである。
私もまた、こうした妄想にふけり、自分の行為を無益と感じることを好むのだ。
※ 寺山氏の書評に関する引用は、すべて「『洞窟の偶像』『東西不思議物語』」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)による。
〔参考〕
※1 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より
榎本了壱デザイン。
※2 「『滞欧日記』の真相」(『新文芸読本 澁澤龍彦』所収)、『澁澤龍彦の古寺巡礼』ほか
※3 『旅のモザイク』あとがきより
ただし「いったん旅の軌道に乗ってしまうと、だんだん上機嫌になって興趣のつきるところを知らない」とも書いている。
※4 『胡桃の中の世界』より
[更新履歴]
'13.12 表現の一部修正
寺山修司と九條今日子さん [BOOK]
今年は寺山修司が47歳でこの世を去ってから30年の、節目の年である。
メディアでは様々な特集が組まれ、所縁の地では若きカリスマを偲ぶ企画が次々と催されている。
かつて「天井桟敷館」があった渋谷では、寺山氏の元夫人・九條今日子さんのトークイベントが開かれた。

(劇団員募集のポスター ※1(左) / ※2)
およそ誇れたことではないが、おそらく会場にいた者の中で、寺山氏に関しては私が最も無知、不案内であったろう。
むろん、その存在感は「劇団・天井桟敷」や「書を捨てよ、町へ出よう」といったキーワードと共に意識していたし、思えば、作品というよりはむしろ人間・寺山修司に対する漠たる興味は、学生来つねに抱いていたような気がする。
だからこそ、このイベントに参加する気にもなったのであるが、一部書評等を除いて作品に接したことがないのもまた事実で、私はまさにファンの方々の“末席”に身を置かせていただいたのであった。
かような次第で、寺山氏について語るに足る材料をほとんど持ち合わせていないので、その人物像や功績についてはウィキさん他にお任せするとして、ここでは九條さんのトークを中心に記すこととする。
九條さんはSKD出身で映画女優をされておられたというのも道理、昨年 喜寿を迎えられたなどとは到底信じられぬほどに若々しく、見目麗しい方であった。
その一方で、ご見解や話しぶりには姉御肌の気風が窺え、清々しい。
時を遡ること半世紀、精気漲る若き劇作家が魅了されてしまったのも、無理からぬ話であろう。

(※3)
交際のきっかけは、SKDの舞台をまさに“天井桟敷”から観た寺山氏が九條さんを見初め、共通の知人を介して、自分が手掛けた舞台に誘ったことに始まる。
九條さんが「前衛的な演出が新鮮で面白かった」と評価するその舞台は、してやったり、彼女に寺山氏を無視できぬ存在として強く印象付けることに成功したのであった。
余談ではあるが、その仲を取り持った知人というのが映画監督の篠田正浩氏、件の舞台『血は立ったまま眠っている』の演出が浅利慶太氏であったというのは、なんとも贅沢な人脈である。
手紙魔の寺山氏は、頻繁に九條さんに文を送っていた。
日中、寺山氏と会い、アパートに戻ると郵便受けに手紙が届いていたというようなことも、間々あったようである。
今時の若者同様、取り留めのない“つぶやき”から甘い恋の“ささやき”まで、その内容は様々であったらしい。
そんな当時の寺山氏を評して、九條さんは「敵は詩人」と表現しておられた。
まだ心を許すまじ、されど、ひとたび気を緩めれば、強烈な飛び道具“愛の詩”の餌食となりうる危険性(あるいは期待か…)をも意識した女心が、九條さんをして「敵」と言わしめたのであろうか。
ある時、九條さんがゴミ箱に捨てていた寺山氏からの手紙を、たまたま部屋に来ていた本人が見つけてしまった。
寺山氏は「文豪の手紙は高くなるから捨てちゃダメだよ。」と言って聞かせたそうである。
また、捌き切れなかった歌集『田園に死す』を古本屋に売ってしまった際も、「俺の本は今に高くなる」と怒られたそうである。
怖いものなしの意気盛んな寺山氏と、負けず劣らずの強者ぶりを発揮する九條さんとのキャラ対立が微笑ましいエピソードである。
微笑ましいついでに、寺山氏のお茶目な姿をもう一つ。
氏は本屋に行くと、自分の本の背を何冊か、少しだけ手前に引出していたとか。
まるで誰かが手に取ったよう装って、客の興味を引こうというのである。
本人の弁によると「五木寛之さんのマネ」とのことであるが、はてさて、真偽のほどは…

寺山氏は、高尾の高乘寺に眠る。
九條さんは、ただ「面白そう」との理由から、同じ霊園の寺山氏の墓を見下ろせる場所に、ご自身の墓を購入されたそうである。
そして、その墓石には「天井桟敷」と刻まれている。
かつて寺山氏が舞台の九條さんを見初めたという「天井桟敷」から、いずれ九條さんや志を同じくする方々(※4)が氏を見守ろうというのである。
これほど粋で、これほどお二方に相応しい演出は、往年のカリスマ劇作家を以ってしても成し得たかどうか…
寺山氏の苦笑いする姿が、目に浮かぶようである。
※ ここで取り上げたエピソードについては、九條さんのご著書『回想・寺山修司』に詳しいものもありますが、今回のイベントでの表現を優先させていただいたので、一部ご著書とは内容の異なる箇所があります。ご了承ください。
※1,※3 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より

※2 かつて寺山氏も訪れたという三軒茶屋の居酒屋。
30年経った今も、“町”のあちこちに氏の足跡を見ることができる。
※4 九條さんは、イベントで「入りたい人は、誰でも入ればいい」と仰られていた。ご冗談かとも思ったが、ご著書にも「「天井桟敷」と墓石に刻んでおけば、誰でも望むなら入れるかもしれない」との件がある。
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
メディアでは様々な特集が組まれ、所縁の地では若きカリスマを偲ぶ企画が次々と催されている。
かつて「天井桟敷館」があった渋谷では、寺山氏の元夫人・九條今日子さんのトークイベントが開かれた。

(劇団員募集のポスター ※1(左) / ※2)
およそ誇れたことではないが、おそらく会場にいた者の中で、寺山氏に関しては私が最も無知、不案内であったろう。
むろん、その存在感は「劇団・天井桟敷」や「書を捨てよ、町へ出よう」といったキーワードと共に意識していたし、思えば、作品というよりはむしろ人間・寺山修司に対する漠たる興味は、学生来つねに抱いていたような気がする。
だからこそ、このイベントに参加する気にもなったのであるが、一部書評等を除いて作品に接したことがないのもまた事実で、私はまさにファンの方々の“末席”に身を置かせていただいたのであった。
かような次第で、寺山氏について語るに足る材料をほとんど持ち合わせていないので、その人物像や功績についてはウィキさん他にお任せするとして、ここでは九條さんのトークを中心に記すこととする。
九條さんはSKD出身で映画女優をされておられたというのも道理、昨年 喜寿を迎えられたなどとは到底信じられぬほどに若々しく、見目麗しい方であった。
その一方で、ご見解や話しぶりには姉御肌の気風が窺え、清々しい。
時を遡ること半世紀、精気漲る若き劇作家が魅了されてしまったのも、無理からぬ話であろう。

(※3)
交際のきっかけは、SKDの舞台をまさに“天井桟敷”から観た寺山氏が九條さんを見初め、共通の知人を介して、自分が手掛けた舞台に誘ったことに始まる。
九條さんが「前衛的な演出が新鮮で面白かった」と評価するその舞台は、してやったり、彼女に寺山氏を無視できぬ存在として強く印象付けることに成功したのであった。
余談ではあるが、その仲を取り持った知人というのが映画監督の篠田正浩氏、件の舞台『血は立ったまま眠っている』の演出が浅利慶太氏であったというのは、なんとも贅沢な人脈である。
手紙魔の寺山氏は、頻繁に九條さんに文を送っていた。
日中、寺山氏と会い、アパートに戻ると郵便受けに手紙が届いていたというようなことも、間々あったようである。
今時の若者同様、取り留めのない“つぶやき”から甘い恋の“ささやき”まで、その内容は様々であったらしい。
そんな当時の寺山氏を評して、九條さんは「敵は詩人」と表現しておられた。
まだ心を許すまじ、されど、ひとたび気を緩めれば、強烈な飛び道具“愛の詩”の餌食となりうる危険性(あるいは期待か…)をも意識した女心が、九條さんをして「敵」と言わしめたのであろうか。
ある時、九條さんがゴミ箱に捨てていた寺山氏からの手紙を、たまたま部屋に来ていた本人が見つけてしまった。
寺山氏は「文豪の手紙は高くなるから捨てちゃダメだよ。」と言って聞かせたそうである。
また、捌き切れなかった歌集『田園に死す』を古本屋に売ってしまった際も、「俺の本は今に高くなる」と怒られたそうである。
怖いものなしの意気盛んな寺山氏と、負けず劣らずの強者ぶりを発揮する九條さんとのキャラ対立が微笑ましいエピソードである。
微笑ましいついでに、寺山氏のお茶目な姿をもう一つ。
氏は本屋に行くと、自分の本の背を何冊か、少しだけ手前に引出していたとか。
まるで誰かが手に取ったよう装って、客の興味を引こうというのである。
本人の弁によると「五木寛之さんのマネ」とのことであるが、はてさて、真偽のほどは…

寺山氏は、高尾の高乘寺に眠る。
九條さんは、ただ「面白そう」との理由から、同じ霊園の寺山氏の墓を見下ろせる場所に、ご自身の墓を購入されたそうである。
そして、その墓石には「天井桟敷」と刻まれている。
かつて寺山氏が舞台の九條さんを見初めたという「天井桟敷」から、いずれ九條さんや志を同じくする方々(※4)が氏を見守ろうというのである。
これほど粋で、これほどお二方に相応しい演出は、往年のカリスマ劇作家を以ってしても成し得たかどうか…
寺山氏の苦笑いする姿が、目に浮かぶようである。
※ ここで取り上げたエピソードについては、九條さんのご著書『回想・寺山修司』に詳しいものもありますが、今回のイベントでの表現を優先させていただいたので、一部ご著書とは内容の異なる箇所があります。ご了承ください。
※1,※3 「寺山修司と演劇実験室 天井棧敷」より

寺山修司と演劇実験室 天井棧敷 (Town Mook 日本および日本人シリーズ)
- 作者: 九条今日子
- 出版社/メーカー: 徳間書店
- 発売日: 2013/04/02
- メディア: ムック
※2 かつて寺山氏も訪れたという三軒茶屋の居酒屋。
30年経った今も、“町”のあちこちに氏の足跡を見ることができる。
※4 九條さんは、イベントで「入りたい人は、誰でも入ればいい」と仰られていた。ご冗談かとも思ったが、ご著書にも「「天井桟敷」と墓石に刻んでおけば、誰でも望むなら入れるかもしれない」との件がある。
タグ:本
「小澤征爾さんと、音楽について話をする」 小澤征爾×村上春樹 4 [BOOK]
※ 作品の内容に触れる記述があります。予めご了承ください。
本書は概ね六つの章から成っているが、うち一章は、その怪しさ(ばかりではないが…)が人々を魅了して止まないマーラーについて割かれている。
そも、書店で何気なく手に取った時点でまったく買うつもりなどなかった分厚い新刊書が、ほんの数分後に帰りの荷物に加わっていた一番の理由がここにあった。
まずもって収穫だったのは、実はマーラーは小澤氏のレパートリーとしてポピュラーであり、また、氏が総監督を務めるサイトウ・キネン・オーケストラが、我が国オケではマーラー演奏の先駆けであるという事実を知ることができたことである。
加えて、氏のマーラーに対する姿勢にも、新鮮な驚きがあった。
マーラーについては、ユダヤ人というその出自と、時に“分裂気質”とか“カオス”などとも評される独特の作風から、村上氏も指摘するように「マーラーその人の生涯とか、世界観とか、時代背景とか、世紀末的な省察とか」といった側面からのアプローチを試みるのが、楽曲解釈論としては一般的であろう。
しかし、この点について小澤氏に質すと、「僕はそんなには考えないかもしれない」との答えが返ってくるのであった。
誰もマーラーたり得ぬ以上、聴く側としては民族性や境遇の近い者を以って“翻訳者”の任を負わそうと考えるのが自然であり、同じくユダヤの系譜を辿るワルターやバーンスタインらの人気が高いのは至極もっともである。
音楽評論家である宇野功芳氏の「前者は弟子として、後者は使徒として、彼の音楽に激しく共感した(※)」との言には説得力があったし、事実、彼等の演奏には名状し難い迫力がある。
しかし、小澤氏は言う。
「僕はね、音楽を勉強するときには、楽譜に相当深く集中します。だからそのぶん、というか、ほかのことってあまり考えないんだ。(中略)自分と音楽とのあいだにあるものだけを頼るというか…」
もちろん、本来あるべき一つの姿勢ではあると思うが、バーンスタインがマーラーに取り組むプロセスをアシスタントとして共有し、そのマーラーへの情熱を身を以って感受して来た小澤氏が採る方法としては、ちょっと意外な気がしないでもない。
あるいは、だからこその帰結と捉えるべきであろうか…
マーラーの作品は、楽譜の指示が細かい―すなわち演奏者の自由に任されている余地が少ない―にも拘らず、その実、演奏者によって非常に多彩な表情を見せるというパラドキシカルな側面を有する。
村上氏はこれを「意識的情報が溢れている分、選択肢がより潜在化していく」と表現し、実はこの特異性が、マーラーと出自を異にする演奏家にとって幸いしているのではないかと考察している。
私なりに解釈すると、つまり、スコア上の指示が事細かであることにより民族性などのアドバンテージが抑制される一方で、いわゆる文学で言うところの“行間”での解釈や表現はむしろ活性化し、ここに多様な価値観の介入する余地が残されている、ということのようである。
前稿のバックハウスにせよ、今回のワルター、バーンスタインにせよ、どうも嗜好に保守的な嫌いのある私にとってはたいへん興味深い考察であり、結果的にマーラーの新たな楽しみ方を教示される形となった。

マーラーについてはまだまだ書き足りないところだが、それでは本稿のテーマから外れてしまう。今回はこの辺りにして、本書を読み通しての素朴な感想を…
いずれも世界をフィールドに活躍する大物同士の、クラシックに関する少々マニアックな対談である。時折り、小澤氏の“感性”と村上氏の“論理”が交錯する場面も見られるが、その周囲には一貫して長閑な空気が漂っている。
これは、本書が発行されるに至った経緯が、ビッグネーム二人による対談企画まずありきだったのではなく、両氏の日頃の付き合いの中から自然発生的に生まれたものであったということが大きい。
互いに対する敬意と共に親密さも感じられ、読んでいて心地良い一冊であった。
小澤 (果物を食べる)「うん、これはおいしいね。マンゴ?」
村上 「パパイヤです」
(おわり)
※ 「新版 クラシックCDの名盤」(宇野功芳ほか共著)より
<追記>
先日、小澤氏の体調不良に伴う一年間の活動休止が発表された。ご快癒を切に祈るものである。
![[雨]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/3.gif)
本書は概ね六つの章から成っているが、うち一章は、その怪しさ(ばかりではないが…)が人々を魅了して止まないマーラーについて割かれている。
そも、書店で何気なく手に取った時点でまったく買うつもりなどなかった分厚い新刊書が、ほんの数分後に帰りの荷物に加わっていた一番の理由がここにあった。
まずもって収穫だったのは、実はマーラーは小澤氏のレパートリーとしてポピュラーであり、また、氏が総監督を務めるサイトウ・キネン・オーケストラが、我が国オケではマーラー演奏の先駆けであるという事実を知ることができたことである。
加えて、氏のマーラーに対する姿勢にも、新鮮な驚きがあった。
マーラーについては、ユダヤ人というその出自と、時に“分裂気質”とか“カオス”などとも評される独特の作風から、村上氏も指摘するように「マーラーその人の生涯とか、世界観とか、時代背景とか、世紀末的な省察とか」といった側面からのアプローチを試みるのが、楽曲解釈論としては一般的であろう。
しかし、この点について小澤氏に質すと、「僕はそんなには考えないかもしれない」との答えが返ってくるのであった。
誰もマーラーたり得ぬ以上、聴く側としては民族性や境遇の近い者を以って“翻訳者”の任を負わそうと考えるのが自然であり、同じくユダヤの系譜を辿るワルターやバーンスタインらの人気が高いのは至極もっともである。
音楽評論家である宇野功芳氏の「前者は弟子として、後者は使徒として、彼の音楽に激しく共感した(※)」との言には説得力があったし、事実、彼等の演奏には名状し難い迫力がある。
しかし、小澤氏は言う。
「僕はね、音楽を勉強するときには、楽譜に相当深く集中します。だからそのぶん、というか、ほかのことってあまり考えないんだ。(中略)自分と音楽とのあいだにあるものだけを頼るというか…」
もちろん、本来あるべき一つの姿勢ではあると思うが、バーンスタインがマーラーに取り組むプロセスをアシスタントとして共有し、そのマーラーへの情熱を身を以って感受して来た小澤氏が採る方法としては、ちょっと意外な気がしないでもない。
あるいは、だからこその帰結と捉えるべきであろうか…
マーラーの作品は、楽譜の指示が細かい―すなわち演奏者の自由に任されている余地が少ない―にも拘らず、その実、演奏者によって非常に多彩な表情を見せるというパラドキシカルな側面を有する。
村上氏はこれを「意識的情報が溢れている分、選択肢がより潜在化していく」と表現し、実はこの特異性が、マーラーと出自を異にする演奏家にとって幸いしているのではないかと考察している。
私なりに解釈すると、つまり、スコア上の指示が事細かであることにより民族性などのアドバンテージが抑制される一方で、いわゆる文学で言うところの“行間”での解釈や表現はむしろ活性化し、ここに多様な価値観の介入する余地が残されている、ということのようである。
前稿のバックハウスにせよ、今回のワルター、バーンスタインにせよ、どうも嗜好に保守的な嫌いのある私にとってはたいへん興味深い考察であり、結果的にマーラーの新たな楽しみ方を教示される形となった。

マーラーについてはまだまだ書き足りないところだが、それでは本稿のテーマから外れてしまう。今回はこの辺りにして、本書を読み通しての素朴な感想を…
いずれも世界をフィールドに活躍する大物同士の、クラシックに関する少々マニアックな対談である。時折り、小澤氏の“感性”と村上氏の“論理”が交錯する場面も見られるが、その周囲には一貫して長閑な空気が漂っている。
これは、本書が発行されるに至った経緯が、ビッグネーム二人による対談企画まずありきだったのではなく、両氏の日頃の付き合いの中から自然発生的に生まれたものであったということが大きい。
互いに対する敬意と共に親密さも感じられ、読んでいて心地良い一冊であった。
小澤 (果物を食べる)「うん、これはおいしいね。マンゴ?」
村上 「パパイヤです」
(おわり)
※ 「新版 クラシックCDの名盤」(宇野功芳ほか共著)より
<追記>
先日、小澤氏の体調不良に伴う一年間の活動休止が発表された。ご快癒を切に祈るものである。
「小澤征爾さんと、音楽について話をする」 小澤征爾×村上春樹 1 [BOOK]
※ 作品の内容に触れる記述があります。予めご了承ください。
愛書家の方々からは邪道とお叱りを受けるかも知れないが、新刊の小説やエッセイを買う場合、余程のことが無い限り私は文庫版になるのを待つ。
元より内容は一緒なわけであるし、適度なインターバルを置くことによって、一時のブームに乗っただけの駄作を掴まされずに済む。
もちろん、「すぐにでも読みたい!」とのモチベーションがあれば、話は別である。
この本は、そんな思いから、久しぶりにハードカバーでの購入となった。
まず驚かされたのは、村上氏のクラシックリスナーとしての“素養”である。
「その昔ピアノを少し習っていた」以外は「ほぼまったくの素人」と自身が語るように、演奏者としてクラシックと接してきたわけではないので、例えばスコアの分析や解釈といったような実践的な事柄についての記述は、決して多くはない。
しかし、高校生の頃からレコードを集め始め、暇を見付けてはコンサートに足を運び、特に在欧中は「浴びるほど」クラシックを聴いた―というような経験は、氏のリスナーとしての感性や知見を培ったばかりではなく、実演奏の僅かな差異を聴き分けられるほどに、氏の音楽的な聴力をも鍛えていたようである。

数回に渡る対談は、病気療養中の小澤氏の体調とスケジュールに最大限の配慮をした環境を、そのつど村上氏自らが調え、余人を交えずに行われた。
例えば村上氏の自宅でのインタビューは、こんな具合に進む。
まず、特定の楽曲についてのレコードやCDを何枚か聴く。
その中で村上氏が気になった箇所、例えばある演奏におけるソリストとオーケストラの微妙な呼吸のズレについて、小澤氏に質す。
すると、そのソリストの性格や指揮者との関係について、同じ状況を経験した者しか知りえない生々しい証言が、マエストロより飛び出す。
また、村上氏の興味がいくつかのオーケストラの特色に及ぶと、その常任指揮者の個性、時代的な流行やホームの聴衆の好み、さらにはホールの形状による音の違いに至るまで、マエストロの舌は一層滑らかになる。
ひたすらスコアと格闘したという修行時代の話などは、「しんどかった」と言いながらも、どこか楽しそうにマエストロは振り返る。
積み重ねられた研鑽の歴史と未だ冷めやらぬ音楽への情熱が、ここでは村上氏のタクトによって紡がれてゆく。
このような展開は、偏に小澤氏をして「聴き方が深い」と言わしめた村上氏の“素養”あったればこそである。
その鋭敏にして的確な指摘は、事実、私が別に読んだ音楽評論家の論評と比べても遜色なく、この点においては、両氏が企んだ「(レコード)マニアが読んで、なるべく面白くないようなものにしていきましょう」との当ては、見事に外れたと言うほかない。
(つづく)
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
愛書家の方々からは邪道とお叱りを受けるかも知れないが、新刊の小説やエッセイを買う場合、余程のことが無い限り私は文庫版になるのを待つ。
元より内容は一緒なわけであるし、適度なインターバルを置くことによって、一時のブームに乗っただけの駄作を掴まされずに済む。
もちろん、「すぐにでも読みたい!」とのモチベーションがあれば、話は別である。
この本は、そんな思いから、久しぶりにハードカバーでの購入となった。
まず驚かされたのは、村上氏のクラシックリスナーとしての“素養”である。
「その昔ピアノを少し習っていた」以外は「ほぼまったくの素人」と自身が語るように、演奏者としてクラシックと接してきたわけではないので、例えばスコアの分析や解釈といったような実践的な事柄についての記述は、決して多くはない。
しかし、高校生の頃からレコードを集め始め、暇を見付けてはコンサートに足を運び、特に在欧中は「浴びるほど」クラシックを聴いた―というような経験は、氏のリスナーとしての感性や知見を培ったばかりではなく、実演奏の僅かな差異を聴き分けられるほどに、氏の音楽的な聴力をも鍛えていたようである。

数回に渡る対談は、病気療養中の小澤氏の体調とスケジュールに最大限の配慮をした環境を、そのつど村上氏自らが調え、余人を交えずに行われた。
例えば村上氏の自宅でのインタビューは、こんな具合に進む。
まず、特定の楽曲についてのレコードやCDを何枚か聴く。
その中で村上氏が気になった箇所、例えばある演奏におけるソリストとオーケストラの微妙な呼吸のズレについて、小澤氏に質す。
すると、そのソリストの性格や指揮者との関係について、同じ状況を経験した者しか知りえない生々しい証言が、マエストロより飛び出す。
また、村上氏の興味がいくつかのオーケストラの特色に及ぶと、その常任指揮者の個性、時代的な流行やホームの聴衆の好み、さらにはホールの形状による音の違いに至るまで、マエストロの舌は一層滑らかになる。
ひたすらスコアと格闘したという修行時代の話などは、「しんどかった」と言いながらも、どこか楽しそうにマエストロは振り返る。
積み重ねられた研鑽の歴史と未だ冷めやらぬ音楽への情熱が、ここでは村上氏のタクトによって紡がれてゆく。
このような展開は、偏に小澤氏をして「聴き方が深い」と言わしめた村上氏の“素養”あったればこそである。
その鋭敏にして的確な指摘は、事実、私が別に読んだ音楽評論家の論評と比べても遜色なく、この点においては、両氏が企んだ「(レコード)マニアが読んで、なるべく面白くないようなものにしていきましょう」との当ては、見事に外れたと言うほかない。
(つづく)
「大胯びらき」 J.コクトー (2) [BOOK]
※ 作品の内容に触れる記述があります。予めご了承ください。
さて、主人公ジャックの人となりについては、冒頭からたっぷりと紙幅を割いた記述があるので、ここに興味深いその一面を紹介しよう。
「彼は潜水夫のように重い。
ジャックは海の底をほじくっている。海の底のことなら、彼にはよく分る。そこにいるのが彼の習慣になっている。誰も彼を水面に引っ張り上げてはくれない。人々は彼の存在を忘れているのだ。水面に浮き上がって、潜水兜や潜水服を脱ぐことは、生から死への転化である。しかし、一本の管から送られて来る非現実的な空気が、彼を生かし、ノスタルジーを満たしてくれる。」
要するに、精神的な 「ひきこもり」 である。
精神的、と言うのには理由がある。
ジャックは年増女からの誘惑、友カノとの過ち、さらには劇場随一の人気女優との恋…
行動として、ヤルこたぁしっかりヤッているのだ。
「すべてが一緒に動く時、見かけの上では何も動かない。」
との、何やら物理の法則めいた一節が、しばらく後に登場する。
思考上の慣性の法則により止(とど)まっている “今在る時点” は、時間の経過と共に進化を続けている参照系にあっては、すでに過ぎ去ってしまった一時点である。
それを知ってか知らずか、ジャックは相も変わらず 「海の底をほじくっている」 のである。
それにしても、ジャックの拠りどころが「一本の管から送られて来る非現実的な空気」 とは、まるで今日のネット社会の病理をも見通しているかのような、なんとも巧妙な喩えではないか。
社会化・文明化のプロセスで生ずる個人の籠殻現象は、時の古今を問わず、喉元に引っ掛かった小骨のように、心の健康に無頓着な文明社会に不気味な存在感を主張する。

「たえず傷ついている運命の持主」 たる主人公ジャックに、コクトーが自身を投影していたであろうことは、前に澁澤の解説を引いて述べた。
では、自らの意思でその訳稿を起こした若き日の澁澤に、はたしてジャックへのシンパシーは無かったか。
“異端” などと称される一匹狼的なイメージと表裏して、常に繊細で寂しがり屋の一面が見え隠れしていた澁澤もまた、実は 「ガラスの種族」 ではなかったであろうか。
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
[更新履歴]
'13.03 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
さて、主人公ジャックの人となりについては、冒頭からたっぷりと紙幅を割いた記述があるので、ここに興味深いその一面を紹介しよう。
「彼は潜水夫のように重い。
ジャックは海の底をほじくっている。海の底のことなら、彼にはよく分る。そこにいるのが彼の習慣になっている。誰も彼を水面に引っ張り上げてはくれない。人々は彼の存在を忘れているのだ。水面に浮き上がって、潜水兜や潜水服を脱ぐことは、生から死への転化である。しかし、一本の管から送られて来る非現実的な空気が、彼を生かし、ノスタルジーを満たしてくれる。」
要するに、精神的な 「ひきこもり」 である。
精神的、と言うのには理由がある。
ジャックは年増女からの誘惑、友カノとの過ち、さらには劇場随一の人気女優との恋…
行動として、ヤルこたぁしっかりヤッているのだ。
「すべてが一緒に動く時、見かけの上では何も動かない。」
との、何やら物理の法則めいた一節が、しばらく後に登場する。
思考上の慣性の法則により止(とど)まっている “今在る時点” は、時間の経過と共に進化を続けている参照系にあっては、すでに過ぎ去ってしまった一時点である。
それを知ってか知らずか、ジャックは相も変わらず 「海の底をほじくっている」 のである。
それにしても、ジャックの拠りどころが「一本の管から送られて来る非現実的な空気」 とは、まるで今日のネット社会の病理をも見通しているかのような、なんとも巧妙な喩えではないか。
社会化・文明化のプロセスで生ずる個人の籠殻現象は、時の古今を問わず、喉元に引っ掛かった小骨のように、心の健康に無頓着な文明社会に不気味な存在感を主張する。

「たえず傷ついている運命の持主」 たる主人公ジャックに、コクトーが自身を投影していたであろうことは、前に澁澤の解説を引いて述べた。
では、自らの意思でその訳稿を起こした若き日の澁澤に、はたしてジャックへのシンパシーは無かったか。
“異端” などと称される一匹狼的なイメージと表裏して、常に繊細で寂しがり屋の一面が見え隠れしていた澁澤もまた、実は 「ガラスの種族」 ではなかったであろうか。
[更新履歴]
'13.03 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
「大胯びらき」 J.コクトー (1) [BOOK]
※ 作品の内容に触れる記述があります。予めご了承ください。
初めて世に出た澁澤龍彦の作品は、翻訳本であった。
原典はもちろんフランス文学、ジャン・コクトーの『大胯びらき』がそれである。
時に1954年、澁澤26歳のことであった。
まず、原作者について簡単に触れておこう。
コクトーは小説家のほかに、詩人や画家としての顔を持ち、さらに『美女と野獣』('46)、『オルフェ』('49) などの作品では、映画監督としての才も遺憾なく発揮している。
まさにマルチアーティストといったところだが、自らは “poéte(詩人)” を好んで称していたというエピソードを踏まえ、澁澤は「彼は、詩というものを技術の様式の裡に閉じこめないで、あらゆるものに通じる純粋な魂の状態と解しているらしい。だからこそ、小説に、芝居に、評論に、映画に、あのように多彩な活躍が、(中略)なんの支障もなくつづけられるのだろう」と説いている。
日本でも数年おきに作品展が催されるなど、今なお根強い人気を持つ芸術家である。

(「ジャン・コクトー展」図録 / 2001年)
澁澤は『大胯びらき』の翻訳を浪人中から手掛け、大学を卒業するまでにはほとんど完成させていたという。
それにしては大人の―すなわち、みだりに修辞・修飾を塗り重ねることのないスマートな文章で、非常に洗練されている印象を受ける。
それが澁澤の手柄か、あるいはそもそものコクトーの筆に由来するものか、原書を自力で読み解くことが敵わぬ以上、判断はつきかねるが、読み進める上での軽妙な翻訳レトリックが心地よく、その意味においては澁澤の力に負うところが大きいように思われる。
内容については、訳者たる澁澤の解説がいくつか残っているので、これを引くのが適当であろう。
そも、タイトル『大胯びらき』の言わんとするところは、「舞踏上の術語で、胯が床につくまで両脚をひろげること、(中略)少年期と青年期のあいだの 《大きな距離》 (原題 Le Grand Ecart の本来の意味)を暗示している」のであり、内容を簡述するならば、「少年期から青年期への危険な年齢における、主人公の愛の悲劇を扱ったもので、コクトーの自伝的な小説と言われているもの」とのことである。
(つづく)
<参考>
本書「あとがき」
「ジャン・コクトー ― 作家と作品」 (『大胯びらき』所収)
「一冊の本 コクトー『大胯びらき』」 (『澁澤龍彦全集』第17巻所収)
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
[更新履歴]
'12.02 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
'12.04 画像の差し替え、一部表現の修正
初めて世に出た澁澤龍彦の作品は、翻訳本であった。
原典はもちろんフランス文学、ジャン・コクトーの『大胯びらき』がそれである。
時に1954年、澁澤26歳のことであった。
まず、原作者について簡単に触れておこう。
コクトーは小説家のほかに、詩人や画家としての顔を持ち、さらに『美女と野獣』('46)、『オルフェ』('49) などの作品では、映画監督としての才も遺憾なく発揮している。
まさにマルチアーティストといったところだが、自らは “poéte(詩人)” を好んで称していたというエピソードを踏まえ、澁澤は「彼は、詩というものを技術の様式の裡に閉じこめないで、あらゆるものに通じる純粋な魂の状態と解しているらしい。だからこそ、小説に、芝居に、評論に、映画に、あのように多彩な活躍が、(中略)なんの支障もなくつづけられるのだろう」と説いている。
日本でも数年おきに作品展が催されるなど、今なお根強い人気を持つ芸術家である。

(「ジャン・コクトー展」図録 / 2001年)
澁澤は『大胯びらき』の翻訳を浪人中から手掛け、大学を卒業するまでにはほとんど完成させていたという。
それにしては大人の―すなわち、みだりに修辞・修飾を塗り重ねることのないスマートな文章で、非常に洗練されている印象を受ける。
それが澁澤の手柄か、あるいはそもそものコクトーの筆に由来するものか、原書を自力で読み解くことが敵わぬ以上、判断はつきかねるが、読み進める上での軽妙な翻訳レトリックが心地よく、その意味においては澁澤の力に負うところが大きいように思われる。
内容については、訳者たる澁澤の解説がいくつか残っているので、これを引くのが適当であろう。
そも、タイトル『大胯びらき』の言わんとするところは、「舞踏上の術語で、胯が床につくまで両脚をひろげること、(中略)少年期と青年期のあいだの 《大きな距離》 (原題 Le Grand Ecart の本来の意味)を暗示している」のであり、内容を簡述するならば、「少年期から青年期への危険な年齢における、主人公の愛の悲劇を扱ったもので、コクトーの自伝的な小説と言われているもの」とのことである。
(つづく)
<参考>
本書「あとがき」
「ジャン・コクトー ― 作家と作品」 (『大胯びらき』所収)
「一冊の本 コクトー『大胯びらき』」 (『澁澤龍彦全集』第17巻所収)
[更新履歴]
'12.02 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
'12.04 画像の差し替え、一部表現の修正
続・薔薇に魅せられし者 「中井英夫」 [BOOK]
以前、「薔薇に魅せられし者」とのタイトルで、“薔薇の画家”ルドゥーテを紹介したことがあるが、私に限って言えば、王妃ジョゼフィーヌよりも、ルドゥーテよりも、より薔薇が強く印象付けられている人物がいる。
作家の中井英夫である。
氏の作品に触れたことのある方ならご存知であろう、物語の随所に薔薇が登場するのである。
その“偏愛”を示す作品はいくつかある。
ここでは、作品集 『とらんぷ譚』 に収容されている「薔薇の夜を旅するとき」と題された短編の一部を紹介しよう。
擬人化された薔薇に相対する主人公の想いに、作家の素望が見て取れる。
「全裸に剝かれて土中に降ろされ、(中略) 地下深くに息をつめて、巨大な薔薇の根の尖端がしなやかに巻きついてくるのを待つほどの倖せがあろうか。」
「うずくまり、眼を瞑って、その触手のかすかなそよぎが次第にきつく厳しく裸身をいましめてゆく、栄光の一瞬。」
「これほどの高貴な方が、この醜い、下賤な奴隷に手ずから触れて下さるのだ。」
「最後の最後まで意識は鮮明に保たれ、すでに半ば融けかかりながらも、いまのいま肥料として吸いあげられてゆく至福の刻。」
同化―
それは一つの愛の成就であると同時に、終焉を意味する。
自己のすべてを捧げし時、
そこに、もう愛を詠う者はいない。
まさに究極とも言うべき愛の形である。
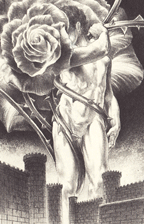
(「とらんぷ譚」挿絵)
この作品で、中井は白薔薇を「白い墓窖※」と喩えている。
その年限りという己の運命を悟った薔薇が、静かに来たるべき時に備えている様を表したものであるが、献身の愛に生きる中井の想いを重ねてみるに、なんとも玄妙な比喩である。
後に、自身の代表作に準えて、『薔薇への供物』という短編集を上梓した中井。
文字どおり、薔薇がモティーフの作品を編んでいるのであるが、むろん中井の考える究極の「供物」は、己自身であったに違いない。
※墓窖(ぼこう)…墓、墓穴
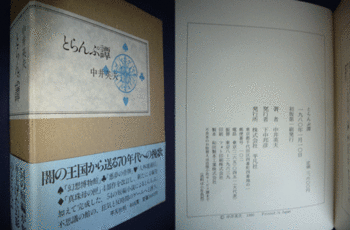
「とらんぷ譚」 (初版 / '80)

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
[更新履歴]
'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
作家の中井英夫である。
氏の作品に触れたことのある方ならご存知であろう、物語の随所に薔薇が登場するのである。
その“偏愛”を示す作品はいくつかある。
ここでは、作品集 『とらんぷ譚』 に収容されている「薔薇の夜を旅するとき」と題された短編の一部を紹介しよう。
擬人化された薔薇に相対する主人公の想いに、作家の素望が見て取れる。
「全裸に剝かれて土中に降ろされ、(中略) 地下深くに息をつめて、巨大な薔薇の根の尖端がしなやかに巻きついてくるのを待つほどの倖せがあろうか。」
「うずくまり、眼を瞑って、その触手のかすかなそよぎが次第にきつく厳しく裸身をいましめてゆく、栄光の一瞬。」
「これほどの高貴な方が、この醜い、下賤な奴隷に手ずから触れて下さるのだ。」
「最後の最後まで意識は鮮明に保たれ、すでに半ば融けかかりながらも、いまのいま肥料として吸いあげられてゆく至福の刻。」
同化―
自己のすべてを捧げし時、
そこに、もう愛を詠う者はいない。
まさに究極とも言うべき愛の形である。
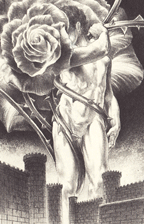
(「とらんぷ譚」挿絵)
この作品で、中井は白薔薇を「白い墓窖※」と喩えている。
その年限りという己の運命を悟った薔薇が、静かに来たるべき時に備えている様を表したものであるが、献身の愛に生きる中井の想いを重ねてみるに、なんとも玄妙な比喩である。
後に、自身の代表作に準えて、『薔薇への供物』という短編集を上梓した中井。
文字どおり、薔薇がモティーフの作品を編んでいるのであるが、むろん中井の考える究極の「供物」は、己自身であったに違いない。
※墓窖(ぼこう)…墓、墓穴
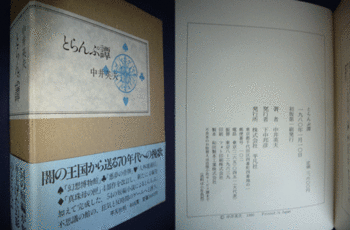
「とらんぷ譚」 (初版 / '80)

幻想博物館 新装版 (講談社文庫 な 3-9 とらんぷ譚 1)
- 作者: 中井 英夫
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2009/12/15
- メディア: 文庫
[更新履歴]
'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
タグ:本
「黒魔術の手帖」 澁澤龍彦 [BOOK]
実家での所用があり、終電前の特急電車に乗った。
急な帰省の知らせだったにも拘らず、古くからの友人が“いつもの店”に集まってくれていた。

※ ハイランドパーク 30y (ダグラスレイン社)
その席で、友人のK君から、今読んでいるという本を見せられて驚いた。
澁澤龍彦の『黒魔術の手帖』。
K君にとっては、澁澤とのファーストコンタクトらしいが、また随分と厄介なものを選んだものである。
『毒薬の手帖』、『秘密結社の手帖』と並んで、いわゆる“手帖三部作”の一つである。
決して難解な内容ではないが、オカルティズムに関する専門的なエッセイであるため、相応のモチベーションがないと読み進めるには骨が折れよう。
美しい細君に瀟洒な戸建て、人もうらやむK君がこの分野に興味があったなどとは、ついぞ聞いたことはなかったのだが…
私が最後に本書を開いたのは、もう5年ほど前、多彩な図録で知られるTASCHEN社の「ALCHEMY & MYSTICISM」を購入した折である。
共通項も多かったので、懐かしくページを繰ったのであった。

さて、『黒魔術の手帖』である。
カバラ信仰にサバト、ローゼンクロイツから、果てはジル・ド・レエ侯…
常に時代の陰となる部分に光を当て続けた澁澤の面目躍如たるラインナップである。
この分野の著述が乏しかった'60年代に出版された意義は大きく、かの三島由紀夫も感嘆し、賛辞を送っている。
曰く、「殺し屋的ダンディズムの本」と。
おそらく、「黒魔術」=『エコエコアザラク』なK君にとっては、馴染みのない記述に戸惑うことも多かろうが、まずは素直な心で、澁澤の博覧強記に酔ってもらいたい。
余談になるが、本書の後半に「ホムンクルス誕生」という章がある。
中世ヨーロッパに、パラケルススという錬金術とも因縁浅からぬ医者がいたのであるが、とある文献によると、彼は放浪の途上で「賢者の石」を手に入れたという。
上記章題に不覚にも反応してしまった“ハガレン”ファンの諸兄には、大いに興味をそそられるエピソードではなかろうか。
ちなみに、パラケルススは、本名を“ホーエンハイム”という。

![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
[更新履歴]
'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
急な帰省の知らせだったにも拘らず、古くからの友人が“いつもの店”に集まってくれていた。
※ ハイランドパーク 30y (ダグラスレイン社)
その席で、友人のK君から、今読んでいるという本を見せられて驚いた。
澁澤龍彦の『黒魔術の手帖』。
K君にとっては、澁澤とのファーストコンタクトらしいが、また随分と厄介なものを選んだものである。
『毒薬の手帖』、『秘密結社の手帖』と並んで、いわゆる“手帖三部作”の一つである。
決して難解な内容ではないが、オカルティズムに関する専門的なエッセイであるため、相応のモチベーションがないと読み進めるには骨が折れよう。
美しい細君に瀟洒な戸建て、人もうらやむK君がこの分野に興味があったなどとは、ついぞ聞いたことはなかったのだが…
私が最後に本書を開いたのは、もう5年ほど前、多彩な図録で知られるTASCHEN社の「ALCHEMY & MYSTICISM」を購入した折である。
共通項も多かったので、懐かしくページを繰ったのであった。

錬金術と神秘主義―ヘルメス学の博物館 (クロッツ・シリーズ)
- 作者: アレクサンダー・ローブ
- 出版社/メーカー: タッシェン・ジャパン
- 発売日: 2004/07
さて、『黒魔術の手帖』である。
カバラ信仰にサバト、ローゼンクロイツから、果てはジル・ド・レエ侯…
常に時代の陰となる部分に光を当て続けた澁澤の面目躍如たるラインナップである。
この分野の著述が乏しかった'60年代に出版された意義は大きく、かの三島由紀夫も感嘆し、賛辞を送っている。
曰く、「殺し屋的ダンディズムの本」と。
おそらく、「黒魔術」=『エコエコアザラク』なK君にとっては、馴染みのない記述に戸惑うことも多かろうが、まずは素直な心で、澁澤の博覧強記に酔ってもらいたい。
余談になるが、本書の後半に「ホムンクルス誕生」という章がある。
中世ヨーロッパに、パラケルススという錬金術とも因縁浅からぬ医者がいたのであるが、とある文献によると、彼は放浪の途上で「賢者の石」を手に入れたという。
上記章題に不覚にも反応してしまった“ハガレン”ファンの諸兄には、大いに興味をそそられるエピソードではなかろうか。
ちなみに、パラケルススは、本名を“ホーエンハイム”という。

黒魔術の手帖 (河出文庫 し 1-5 澁澤龍彦コレクション)
- 作者: 澁澤 龍彦
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 1983/12
- メディア: 文庫
[更新履歴]
'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
“モオツァルトのかなしさ” について [BOOK]
巷ではベートーベンで年を締めくくるのに、このブログはモーツァルトで年を越してしまった。
よもやの成り行きである…謹賀新年。
「モオツァルトのかなしさは疾走する。涙は追いつけない。」
前稿でも触れたが、数多の賛辞も追いつけないこの小林の名評は、特に交響曲第40番に対して為されたというわけではない。
そも、著書 『モオツァルト』 に楽譜の一部が示されているのは「ト短調クインテット K.516」、すなわち弦楽五重奏曲第4番ト短調であるが、これもまた、例を示したにすぎないと考えるのが自然である。
小林がここにいう「モオツァルトのかなしさ」とは、個々の作品―なかんずく既掲の短調作品など―に反映されているモーツァルトの愁いや悲観は言うに及ばず、モーツァルトその人の在り方や生き様に対して抱いている小林自身の想いも込められたものと見るべきであろう。
なればこそ、小林は、ゲオン(あるいはスタンダール)言うところの “tristesse” を追評する際、あえて「かなしみ」ではなく「かなしさ」という言葉を当てたのではなかろうか。
前者の主体はモーツァルトに帰するが、後者のそれは、評者にまで及ぶからである。
小林は「彼は悲しんではいない。ただ、孤独なだけだ。」と言う。
また、「僕には、彼の裸で孤独な魂が見える様だ。」とも。
逆説的な言い回しになるが、小林のこの言が正しいのであれば、モーツァルトは真に孤独であったわけではない。
なんとなれば、国を越え、時代を越え、その最大の理解者がここにいたのであるから。
<追記>
年頭にあたって、ブログ開設当初に目標としていた更新ペースを「1週間に2回」から「2週間に1回」へ、“パッと見”分からない、ほんの微々たる修正をする。
![[晴れ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/1.gif)
[更新履歴]
'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集
よもやの成り行きである…謹賀新年。
「モオツァルトのかなしさは疾走する。涙は追いつけない。」
前稿でも触れたが、数多の賛辞も追いつけないこの小林の名評は、特に交響曲第40番に対して為されたというわけではない。
そも、著書 『モオツァルト』 に楽譜の一部が示されているのは「ト短調クインテット K.516」、すなわち弦楽五重奏曲第4番ト短調であるが、これもまた、例を示したにすぎないと考えるのが自然である。
小林がここにいう「モオツァルトのかなしさ」とは、個々の作品―なかんずく既掲の短調作品など―に反映されているモーツァルトの愁いや悲観は言うに及ばず、モーツァルトその人の在り方や生き様に対して抱いている小林自身の想いも込められたものと見るべきであろう。
なればこそ、小林は、ゲオン(あるいはスタンダール)言うところの “tristesse” を追評する際、あえて「かなしみ」ではなく「かなしさ」という言葉を当てたのではなかろうか。
前者の主体はモーツァルトに帰するが、後者のそれは、評者にまで及ぶからである。
小林は「彼は悲しんではいない。ただ、孤独なだけだ。」と言う。
また、「僕には、彼の裸で孤独な魂が見える様だ。」とも。
逆説的な言い回しになるが、小林のこの言が正しいのであれば、モーツァルトは真に孤独であったわけではない。
なんとなれば、国を越え、時代を越え、その最大の理解者がここにいたのであるから。
<追記>
年頭にあたって、ブログ開設当初に目標としていた更新ペースを「1週間に2回」から「2週間に1回」へ、“パッと見”分からない、ほんの微々たる修正をする。
[更新履歴]
'11.10 モバイル端末での閲覧用に改行・編集














